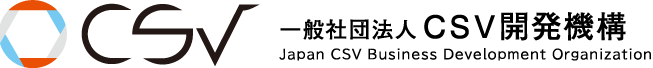脱炭素時代の新しいまちづくりを考える
官民連携による『かわさきカーボンゼロチャレンジ』の推進


CSV開発機構の2022年3月の全体セッションは、川崎市との共催でオンラインセミナー形式で開催されました。
川崎市は政令指定都市としては日本で初めて「カーボンゼロ」を掲げた自治体であり、産業界も巻き込んだ脱炭素の取り組みを広げています。当機構も川崎市の活動に賛同、協力してきた経緯もあり、今回の共催となりました。
はじめに、菌類を利用して木からエネルギーやマテリアルを取り出す研究の第一人者で、いち早く日本に「バイオエコノミー」を紹介した東京大学農学生命科学研究科の五十嵐圭日子教授が基調講演を行ったほか、川崎市の脱炭素の取り組みについて、各課の課長からご報告いただきました。
※このレポートは3回に分けてご報告いたします。
本セミナーの講演者の投影資料はこちらからダウンロードが可能です。
基調講演
「まちの構造を見直し、脱炭素社会を楽しく実現する 」
東京大学 大学院 農学生命科学研究科 五十嵐 圭日子教授
気候は「未病」の状態
五十嵐教授の専門は生物材料科学で、木や草などの自然のものから、セルロースナノファイバー、バイオ燃料、バイオプラスチック、CLT等の集成材などのエネルギーや物質を取り出す研究に取り組んでいる。かつては「何のために木を使うのか」という議論が中心だったが、技術が発展した現在は、「どんどん木を使っていきましょう」という議論になり、大いに盛り上がっているのだという。
「中でも、キノコなどの菌類の研究に力を入れています。菌類は地球上で唯一木を分解できる生物で、その酵素を利用すると常温で木を溶かしたり、さまざまな物質を取り出して使ったりもできます。それを使って、循環型社会としてのバランスを取る。それが、私がメインで取り組んでいることのひとつです」
五十嵐教授は、このような基礎研究を実社会に転用、産業化する手法を学ぶために、2016年からはVTTフィンランド技術研究センターの客員教授を兼任している。
そして、五十嵐教授のもうひとつのバックグラウンドが「気候」である。2006年に元米国副大統領のアル・ゴア氏が創設した「The Climate Reality Project」が認定するClimate Reality Leaderの資格を持っており、気候変動の事実を正確に踏まえ、まちづくりに活用していく活動にも取り組んでいる。五十嵐教授は現在の気候を「未病の状態だ」と指摘する。未病とは病気の一歩手前を指すが、気候の未病とは「ゆらぎ」が大きくなる状態を指すという。
「皆さんも『地球温暖化』という言葉を耳にしていると思いますが、これは人間の未病と同じ状態。若い頃は徹夜したり、飲みすぎたりしても次の日にはケロッとして正常な状態に戻りますが、年を重ねると飲みすぎたりすると次の日大変なことになる。つまり、ゆらぎが大きくなる。気候でいえば、いきなり寒くなって雪が降ったり、非常に暑くなったりする。そういう状態が続いています」
「気候変動」とは、このゆらぎの大きい状態を指す。問題は、このゆらぎがさらに大きくなれば向こう側=病気のほうに転がり落ちてしまうことだ。それが「気候危機」「気候崩壊」と呼ばれる状況である。その兆しは至るところに現れており、北極の氷が溶けて北極点のポールがぷかぷかと浮かぶ事象が確認されたり、日本でも桜の満開時期が過去1200年中でもっとも早くなっていたりするなど枚挙の暇がないほどだ。国立環境研、海洋研究開発機構などが、温暖化の進展をシミュレートしたところ、“No Action”だと2100年までに気温は12度上昇し、極地の氷は溶け出すが、パリ協定を実現すれば、「いくらかましな状態で2100年を迎えることができる」と五十嵐教授。
「昔は本当に温暖化するのか、どうなるのかという議論ばかりしていましたが、現在はもう、確実にこうなることが分かっていて、それをどう食い止めるのか。このままでは次世代に間違いなく禍根を残すことになる。なんとかして正常な状態に戻すのが科学者のミッションだと思っています」
炭素と経済
また、気候変動は環境問題から経済の問題へと、その意義を大きく変えつつあるとも指摘します。1850年から2010年までに、化石燃料由来の二酸化炭素排出量は1821ギガトン。これに対し、今後利用可能な化石燃料の埋蔵量は、燃焼・排出する二酸化炭素量に換算すると2795ギガトン相当あるとされる。この埋蔵量に基づいて企業は投資をしているが、それは決して戻ってくることのない投資なのだと五十嵐教授。
「約2800ギガトンの埋蔵量を見越して100年大丈夫だ、200年大丈夫だと考えているようですが、温暖化が進行すれば、あと10数年で化石燃料が燃焼不能になってしまう。なのに今、すべての化石燃料が燃焼可能だという前提で投資が行われており、その額は22兆ドルとも言われています。日本だけでも7兆8000億円のマイナスです」
アル・ゴア氏はそれを「サブプライム炭素バブル」と名付け、いずれリーマンショックのような炭素の破綻が訪れるとした。日本の場合、石炭火力発電関連施設が、最大で710億ドルの座礁資産になるという予測もされているのだという。 「つまり、炭素のコストが、世界経済にとって最大の脅威になっているということです。温暖化、気候変動とは環境問題で、なんとか克服すれば良いというマイルドな感じに捉えられていたと思いますが、克服できなかったときの経済的なマイナスが、とんでもないことになるというように問題の内実が変わってきていると言えるでしょう」
日本は、2030年までに2013年度比で排出量を46%、重量で680メガトンの二酸化炭素排出量削減が目標となっている。もし、この目標が達成されない場合、EUの排出量取引(EU-ETC)で考えると、2021年の価格で計算しても年間3兆5000億円を支払うことになる。また、日本は年間2億リットルの石油を利用しているが、原油価格が1バレル200ドルになると、GDPの5%に相当する年間29兆円が海外に流出することになる。
「原油価格は今後さらに倍倍と上昇する可能性もあるし、GDPの5%と言っていますが、GDPは減る一方です。こういうことを考えると、脱炭素が単なる環境問題ではなく、達成できなかった場合のペナルティも含めて大きな経済的な問題であるということがお分かりいただけたのではないかと思います」
二酸化炭素等の温室効果ガス(GHG)の削減目標46%を川崎市に当てはめた場合、年間2139万トン。これをEU-ETCで換算すると、現在の相場50ユーロ/トンなら650億円相当だが、2030年には100ユーロ/トンになるとも言われており、その場合1200億円にものぼる。これは川崎市の年間予算の約10%。「稼いだお金の10%を二酸化炭素のために払うなんて、この先本当に私たちがやるべきことなんでしょうか、ということなんです」と五十嵐教授は言う。
また、GHG排出量削減の費用は「炭素税」という形で負担されることになるが、広大な森林を持つ岩手県と、森林を持たない東京都の人が同じように負担するべきなのかという問題も生じてくる。
「国境炭素税と同じように、都道府県間でもやり取りする必要が出てくるでしょうし、この考え方は企業間、もっと言えば家庭間でも生じることになるでしょう。今後10年くらいで、経済負担や価値観が大きく変わろうとしています」
バイオエコノミーと未来
森林のない都市部でもGHG排出量を減らすには「木材を長く使う」「木質化」「再生可能エネルギー利用」という考え方が重要になる。五十嵐教授が専門とする菌類研究も、木材を長く使うことを目的にしており、このような自然のものを利用し、低炭素・持続可能・環境低負荷のものを広く「バイオエコノミー」と呼ぶ。
バイオエコノミーの概念は2009年にOECDで提唱されたもので、EUでは広く普及しており、「(バイオエコノミーの)目的は、生物の多様性と環境の保護を確保しながら、持続可能な農業と漁業、食物セキュリティ、再生可能な生物資源の産業のための持続可能な使用を、より革新的で低排出の経済と調和させること」と定義されている。
そして、フードセキュリティ、化石燃料に依存した経済からバイオ素材への移行、未利用の海洋資源の活用の3点が主要なテーマとして掲げられている。日本では「バイオ」といえば医療、ヘルスケア、遺伝子組み換えなどのイメージが強く、バイオエコノミーの受け入れも遅かったが、ようやく2019年に立案された政府のバイオ戦略「2030年のバイオエコノミー社会」でバイオ素材、持続的一次生産システム、スマート林業など幅広いバイオエコノミーが盛り込まれ、大きく動き始めようとしている。
ヨーロッパではすでに多様なバイオエコノミーのあり方が模索され、一部では実用化、社会実装もされつつある。2018年のグローバル・バイオエコノミー・サミットでは、昆虫を利用したパスタ、菌類=キノコから作る「マッシュルームプラスチック」や「マッシュルームレザー」による製品などが紹介された。他にもEU各国が進めるバイオエコノミー戦略では、竹から作るディスポーザルな食器、バイオプラスチックで作るトイレブラシや自転車のフレームなど多種多様なアイテムが出始めているという。
出発物質や基礎的なマテリアルへの利用も進む。菌類研究の応用で、ヘッドフォンのすべての素材を菌類・微生物を利用して製造するプロジェクトがある。プラスチック、スポンジなどすべての部品が自然由来の素材で作られる。
「従来のヘッドフォンとまったく同じ使い勝手だが、唯一困るのがキノコの匂いがすること(笑)」なのだとか。木から布を製造する技術、染料を抽出する技術も開発され注目を集めている。
夢物語みたいだと思われるでしょうか。
しかし、これはもう現実のものとして広まりつつあるもの。変換技術のバイオ化、出発物質も含む原料のバイオ化が進んでいますが、この先一番大切なのが、評価のバイオ化です。
これまでは経済性重視、安ければ良いとされてきましたが、この安さは本当の安さではなかった。生態系や地球が壊れたときに支払わなければならない費用までも含めた経済性を考える。そういう価値観にシフトしていかなければなりません」
バイオエコノミーを推進する新しい言葉として、2020年ころからEUでは「ネイチャーポジティブ」が使われるようになったという。生物多様性のみならず、自然全般がポジティブであることを指向する言葉だ。
また、サーキュラーエコノミーが推奨されるようにはなったものの、もっと一人ひとりの生活に根ざした循環にならなければならないと五十嵐教授は言う。
「チキンサラダを食べたいと思ったときに、これまでの経済活動では食べたいと思う量以上が生産され、流通し、販売されて成り立っていましたが、この先は、川崎の人が何グラムのチキンサラダを食べれば良いのか?というところからスタートしようということ。そうすれば余剰、フードロスがない、もう一段うえのサーキュラーエコノミーが可能になるはず。その循環の至るところにバイオエコノミーが組み込まれている、『サーキュラーバイオエコノミー』の実現が目指す社会のあり方です」
その社会では、化石燃料依存から脱し、エネルギー、素材がバイオ化し、バイオプロダクトが作られるようになる。人々は適切なプロダクトに支えられ、ウェルビーイングな暮らしを求めるようになるだろう。バイオエコノミーは環境問題にとどまらず、経済の問題であり、人々の生活に直結し、まちづくりにも深く関わることになる。
日本では、佐賀市がいち早くバイオエコノミーに取り組み始めている。廃棄物の資源化、エネルギーへの循環活用を進めており、サーキュラーバイオエコノミーの教育にも力を入れている。2019年にはVTTフィンランド技術研究センター、東京大学と連携したワークショップなども実施した。企業では、味の素がバイオリサイクルで実績を上げつつあるなど、徐々に日本でもバイオエコノミーの活動は広がりつつある。五十嵐教授は、最後に次のように川崎市への期待を述べて締めくくった。
「地球はあと100年保たないんじゃないかと言われています。100年後の地球を考えるために、自分の専門だけでなく、他の分野とも連携し、最終的には地球の未来を存続させる手段を見つけ出したいと思っています。そして、その考えを教育で次世代につなげ、より良い社会、まちづくりを実現していきたい。川崎市さんも同じように考えているはずですから、ご一緒できることがあるんじゃないかと期待しています」
続いて川崎市の皆さんからの講演内容はこちら